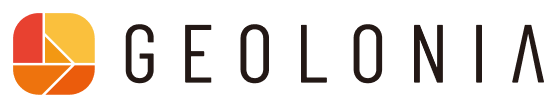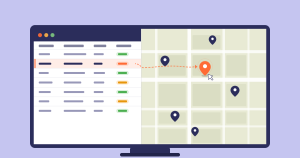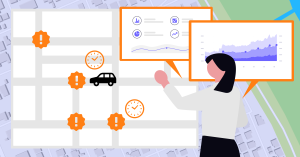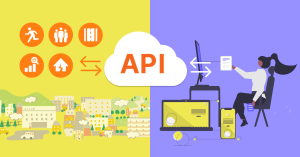台帳と地図を“同じ画面”で扱うと、現場の判断が速くなる新着!!
「その案件、結局どこだっけ?」 自治体の業務では、道路の補修要望、通学路の危険箇所、被害状況の報告、開発許可申請など、「場所」に紐づく情報を日常的に扱っています。しかし多くの現場では、こうした情報を台帳(Excel等)で […]
「避難所はどこ?」の次に聞かれることに、デジタルで答える方法ーー開設・混雑情報のデータ化
災害対応の現場で、住民から多く寄せられる問い合わせは「避難所はどこですか?」で、その次にはこういった質問が続きます。 「今、開いていますか?」「もう満員ですか?」「ペットと一緒に入れますか?」 ところが現場の実情はどうで […]
観光DXの“その次”へ。スポットデータを「作って終わり」にしない更新運用の回し方
観光パンフレットをPDFのまま配るのではなく、データ化して地図に載せ、Webで検索できるようにする。ここまで進めば、観光DXは大きな一歩を踏み出したと言えます。 しかし、公開して数カ月もすると、現場では次のような「あるあ […]
通学路DXの「その先」へ。危険箇所データを“都市の資産”に変える、発見・改善・検証のサイクル
デジタル化はゴールではなく「スタート」 多くの自治体で、通学路の安全点検業務のデジタル化が進んでいます。 以前の記事(通学路の「紙と手作業」を卒業。デジタル化で実現する持続可能な安全管理)でもご紹介した通り、紙の地図やハ […]
観光DXは“地図”から始まる〜「使われないPDF」を「稼げる観光資源」に変える方法〜
観光マップが「PDFのまま」止まっていませんか? 多くの自治体が、観光施策の一環として「観光マップ」や「スポット紹介ページ」を整備しています。地元の名所・飲食店・体験施設・宿泊施設など、そこには地域の魅力が詰まっています […]
災害時に住民の命を守る地図とは?〜「貼るだけ」のハザードマップから行動を支えるGISへ〜
発生する災害から考える:「あるけど使えない地図」では意味がない 毎年のように発生する豪雨災害や地震。自治体はその度に、迅速な情報提供と判断を迫られます。多くの自治体ではハザードマップや避難所一覧を整備していますが、「紙の […]
通学路の「紙と手作業」を卒業。地図データ化で教育現場の業務負担を軽減する
子どもの安全を守る「通学路点検」が、現場の重い負担に 子どもたちの登下校の安全を守るために、全国の小学校や教育委員会では毎年「通学路点検」が行われています。地域や関係機関との連携、交通安全の強化、防災対策との接続など、極 […]
機械判読性のある地図が変える防災の実装事例:高松市「マイセーフティマップ」
以前「機械判読性のある地図」の記事でもご紹介しましたが、地図を「人が読む」紙ベースのものから「コンピュータが理解できる」データへ変える取り組みが、スマートシティや自治体DXの鍵となる「機械判読性のある地図」です。 今回は […]
APIって何? 地図データの活用が変えるスマートシティ
近年、「スマートシティ」や「自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)」といった文脈でよく聞かれるようになった「API」という言葉。しかし、実際にどのような仕組みで、何が出来るようになるのかは、意外と知られていないか […]
自治体標準オープンデータセットとは?DXを加速させる「標準化」の力
オープンデータをうまく活用したいけれどフォーマットがバラバラで扱いにくく、例えば「防災担当者が隣接市町の避難所データと比較しようとしたら、項目名がバラバラで困った」という経験はありませんか?そんな課題を解決するため、デジ […]