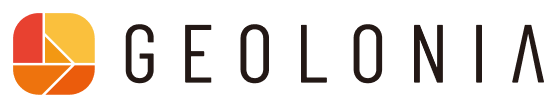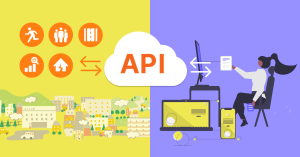自治体標準オープンデータセットとは?DXを加速させる「標準化」の力
オープンデータをうまく活用したいけれどフォーマットがバラバラで扱いにくく、例えば「防災担当者が隣接市町の避難所データと比較しようとしたら、項目名がバラバラで困った」という経験はありませんか?そんな課題を解決するため、デジタル庁が推進している取り組みが「自治体標準オープンデータセット」です。
この記事では、この標準データセットの概要や注目されている理由、そして具体的な活用事例について、わかりやすくご紹介します。
標準オープンデータセットって、どんなもの?
これまで、自治体がそれぞれ独自の形式でオープンデータを公開してきた結果、例えば避難所の位置情報を得るために、自治体ごとに異なるフォーマットのファイルを開いて確認する必要がありました。そんな手間をなくすために登場したのが特定のテーマごとに「この項目を、この形式で公開しましょう」というルールを国が定めた「自治体標準オープンデータセット」です。
たとえば、
- AED設置場所
- 避難所
- 公園や観光施設
など、全国どこでも共通フォーマットで公開されることで、「比較しやすい」「組み合わせやすい」「再利用しやすい」データ環境が整っていきます。
なぜ「標準化」が自治体DXに不可欠なのか?
オープンデータの標準化は、スマートシティの推進や自治体DXにおいて極めて重要な意味を持ちます 。
- データ連携がしやすくなる: 形式がそろっていれば、異なる自治体同士や民間システムとのデータ連携がスムーズになります。
- アプリ開発がラクに、広く使える「A市向けに作ったアプリが、B市でもそのまま動く」そんなことが現実になります。開発コストも下がり、よりよいサービスが全国へ広がりやすくなります。
- AIやIoTとの連携がしやすくなる: たとえば、「AED設置場所」と「人口動態」を組み合わせて、AIが最適な設置エリアを提案するなど、高度な分析も現実的になります。
- ベンダーロックインを回避できる: 特定ベンダーに依存せず、自由なシステム選定が可能になります。自治体にとって「しなやかなデジタル基盤づくり」に直結します。
標準化されたデータで何ができる?5つの活用分野
標準化されたデータがあることで、こんな分野でも実際に使われはじめています。
- 防災
- 統一形式で公開された避難所やハザードマップ情報を活用し、住民向け防災アプリの開発
- 位置情報と連動した避難案内や、過去の災害情報との比較分析による、避難計画の策定容易化
- 子育て支援
- 公園、保育施設、医療機関などの情報を一元的に公開
- 引っ越してきた家庭も、すぐに地域の情報が把握できるポータルサイトやアプリの構築
- 観光振興
- 観光施設やイベントや施設、交通機関の運行状況を標準化データで提供
- 経路最適化アプリや観光マップの開発にも活用
- 都市計画・まちづくり
- 土地利用計画、道路情報、公共施設配置等のデータを活用した都市のデジタルツイン構築
- 将来の人口変化や災害リスクをシミュレーションした、よりよい都市計画の策定
- 地域経済活性化
- 地域の店舗やイベント情報を外部サービスと連携
- 情報発信や新しいプロモーション戦略の立案
Geoloniaが提供できる価値〜標準データセットを「活かせる形」に〜
Geolonia は、自治体が保有するさまざまなデータを、自動で収集・変換し、API や地図タイルとして配信する「地理空間データ連携基盤」を提供しています。これにより、自治体標準オープンデータセットの普及と活用を強力に後押しします。
- 標準データセットの「自動収集・活用」: 自治体が整備した標準データセットから、基盤が自動で収集し、地図タイルによるAPI配信という活用しやすい形式で配信します。これにより、単にデータを公開するだけでなく、様々なアプリケーションと連携・活用できるようになります。
- データ更新の自動化: 国の標準データセットに変更があった場合も、基盤が自動でキャッチアップし、アプリケーションに常に最新情報を反映反映させます 。
- 地理空間情報との連携強化: 地理空間データ処理技術を最大限に活かし、データの「統合」「可視化」「再利用」をより高度なレベルで実現します 。
自治体標準オープンデータセットの取り組みは、これからの自治体DXを加速させる鍵となります 。Geoloniaは、これからの更なるデータ活用時代に向けて、現場に寄り添いながら、分かりやすく持続可能なデータ基盤作りをサポートしていきます。まずはお気軽にご相談ください。
自治体の方、自治体向けにデータ連携サービスを提供されている方、メディアの方など
こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。