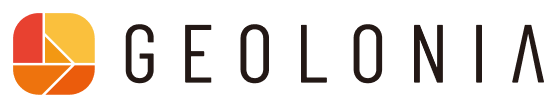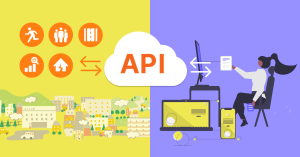機械判読性のある地図が変える防災の実装事例:高松市「マイセーフティマップ」
以前「機械判読性のある地図」の記事でもご紹介しましたが、地図を「人が読む」紙ベースのものから「コンピュータが理解できる」データへ変える取り組みが、スマートシティや自治体DXの鍵となる「機械判読性のある地図」です。
今回はその具体的な活用事例として、高松市で導入された防災アプリ「マイセーフティマップ」を取り上げ、機械判読性のある地図がどのように役立つのかを解説します。
紙のハザードマップでは実現が難しかった、リアルタイムな防災情報の共有。その壁を越えるために活用された仕組みを紹介します。
従来のハザードマップの課題
災害に備えて多くの自治体がハザードマップを作成・配布していますが、紙やPDFベースの地図には次のような課題がありました。
- 更新の手間:土地利用の変化や新たな災害知見をすぐに反映できない
- リアルタイム性の欠如:発災時の状況変化を住民に届けるには限界がある
- 表現の制約:浸水深や継続時間など複雑な情報を地図上で分かりやすく表現しきれない
これらの課題を乗り越えるには、地図を構成する要素を「機械が処理できるデータ」として整備することが鍵となります。つまり、見た目のデザインよりも地図の「構造」が重要となります。
「マイセーフティマップ」の仕組みと特長
高松市がGeoloniaとともに開発・公開した「たかまつマイセーフティマップ」は、機械判読性のある地図を前提とした防災アプリケーションです。
このアプリでは、次のようなデータが自動で連携され、地図上に可視化されています。
- オープンデータ:避難所、医療機関、学校などの施設情報を、高松市のオープンデータから自動で取得
- ハザードマップ情報:浸水区域などの災害リスクを、地理情報データから取得し地図上に表示
- リアルタイムセンサー情報:河川水位や潮位、冠水などの状況をセンサーから取得し、地図上に可視化
- タップで災害リスク確認:地図上の任意の場所をタップすると、浸水深や継続時間などのリスクを即座に表示
これらはすべて、地図を構成する各要素が「機械判読可能」な形式で整備されているからこそ実現できる仕組みです。

右はコンピューターが理解するためのデータで、左はそのデータを人間が見るためにために表現された地図
なぜ「機械判読性」がカギなのか
この「マイセーフティマップ」の仕組みの核心は、地図を「見た目の情報」としてではなく、「構造化されたデータ」として扱うことです。
紙の地図では、浸水区域を示す色や文字は人間が読むためのものであり、コンピューターにとっては単なる画像です。しかし、機械判読性のある地図では、その色や文字の一つひとつが、「ここは浸水深50cmのエリア」「これは避難所として利用可能な建物」という意味と座標を持ったデータとして整備されています。
これにより、アプリやシステムは以下のことが可能になります。
1. データの「結合」によるリアルタイムな判断
機械判読可能なデータは、種類が違ってもプログラム上で簡単に組み合わせることができます。
- 紙の地図: 浸水エリア図と、川の水位計(センサー)を別々に見て、自分で状況を判断する。
- 機械判読可能な地図: 「浸水エリアのデータ」と「リアルタイムの水位計データ」をアプリが自動で結合し、「今、あなたのいる場所の近くの川が氾濫危険水位に達している」というリアルタイムな警告をコンピューターが判断、即座に表示してくれる。
2. アプリ開発・サービス連携の自由度
データが構造化されているため、特定のアプリに依存せず、多様なサービスで再利用できます。
たとえば、浸水区域のデータを機械が読める共通の形式で提供すれば、別の企業が開発した経路検索アプリがそのデータを取り込み、「危険なエリアを避けた避難ルート」を自動で計算して提案できるようになります。
このように、機械判読性のある地図は、防災対応のスピードと正確性を飛躍的に向上させ、将来のスマートシティ構築を可能にするための、基盤となるデータインフラなのです。
現場での活用と住民メリット
高松市では、「マイセーフティマップ」が発災時や市民向け広報に積極的に活用されています。具体的には
- 発災時に頼れるツール:水位センサーと連携し、河川の状況をリアルタイムで可視化
- 誰でも使いやすいUI:スマホ向けに最適化されており、高齢者をはじめどの世代でも直感的な操作が可能
- 避難計画の検討に活用:自宅周辺の浸水深や浸水継続時間を確認し、避難経路を見直せる
また、データが常に更新されるため、紙の地図のように「古くなる心配」がありません。
防災の未来は、データのかたちから始まる
「マイセーフティマップ」は、機械判読性のある地図がもたらす防災の未来を具体的に示す事例です。
- データがつながれば、情報は常に最新に保たれる
- 地図は「人に見せるもの」から「機械が動かすもの」へ
- 直感的に使えるUIと、拡張性のある仕組みが両立可能に
この流れは、特定の自治体にとどまらず、全国に広がる可能性を秘めています。これからの防災は、まず「地図のかたち」から見直してみる必要があるのかもしれません。
自治体の方、自治体向けにデータ連携サービスを提供されている方、メディアの方など
こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。