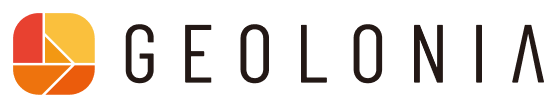機械判読性のある地図とは? スマートシティを支える新しい地図のカタチ
「データ駆動型社会」や「スマートシティ」という言葉を耳にする機会が増えましたが、これからの都市づくりにおいて、私たちの生活に不可欠な「地図」の役割が大きく変わりつつあります。単に場所を示すだけでなく、コンピュータが理解し、活用できる「機械判読性のある地図」が、都市の課題解決に不可欠な要素となりつつあります。
本記事では「機械判読性のある地図」の概念と必要性、そして具体的な活用事例を取り上げながら、その可能性を紐解いていきます。
地図の進化:紙からデジタル、そして機械判読性へ
私たちが日常的に利用する地図は、時代とともに進化してきました。
- 紙の地図: 視覚的に直感的で誰でも情報を読み取れる一方で、一度印刷すると情報の更新が難しく、リアルタイムの変化を反映できません。また、多くの情報を集約するのにも限界があります。
- 一般的なデジタル地図: Googleマップなどに代表されるデジタル地図は、GPS機能と連動して現在地を表示するなど、利便性が飛躍的に向上しました。しかし、これらは人間が見やすいようデザインされており、コンピュータが直接理解・分析するには多くの課題が残ります。
- 機械判読性のある地図: ここで登場するのが「機械判読性のある地図」です。これは、地図そのものが単なる画像ではなく、コンピュータが内容を理解し、解析・処理できるデータ構造を持つ地図を指します。地図上の情報(道路、建物、避難所など)が、それぞれが持つ属性情報(名称、住所、耐震性など)と紐づいたデータとして整備されています。これにより、コンピュータは地図を「データ」として認識し、自動的に様々な処理を行うことが可能になり、例えば以下のようなことが実現可能になります。
- 位置を指定して建物の名称や住所、建物の種類、耐震性などの属性情報を取得
- 「収容人数が100人以上の避難所」や「土砂災害の時に利用できる避難所」など特定の条件に合致する情報だけを地図上に表示
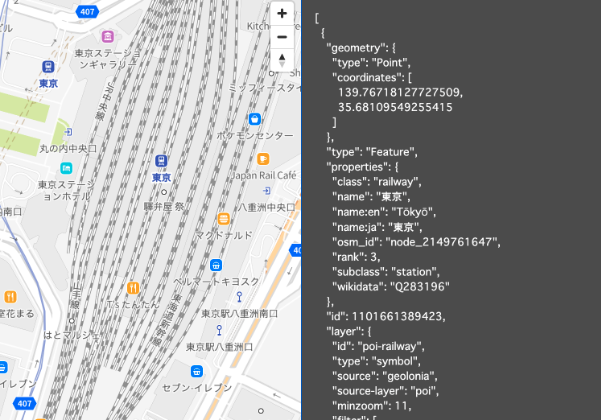
なぜ今、「機械判読性」が重要なのか?
機械判読性のある地図は、スマートシティや自治体DXを推進する上で不可欠な要素です。従来の地図が抱える以下の課題を解決する鍵となります。
- データ活用の非効率性: 自治体や民間企業が保有する様々な地理空間情報は、Excelや画像、PDFといった異なる形式でバラバラに管理されているため、横断的な活用が困難です。
- アプリケーション開発の非効率性: 新しいサービスを開発するたびに、データ収集・整備から始める必要があり、時間、コスト、人的リソースの負担が大きくなります。GeoJSONやベクトルタイル、データPNGといった機械可読な形式でデータが整備されていれば、Webアプリケーションへの埋め込みやAIによる解析といった高度な活用が現実のものになります。
- 市民サービスの停滞: データの壁や開発コストの高さから、防災、子育て支援、観光振興といった市民生活に直結するサービスがなかなか充実しないという問題があります。
自治体の方、自治体向けにデータ連携サービスを提供されている方、メディアの方など
こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。
「機械判読性」の実装事例:たかまつマイセーフティマップ
高松市では、Geoloniaの地理空間データ連携基盤を活用した「たかまつマイセーフティマップ」が導入されています。このサービスは、機械判読性を前提に設計されており、従来の防災情報が抱えていた課題を革新的に解決しています。
たとえば、紙のハザードマップは一度印刷されると情報の更新が難しく、発災時に刻々と変わる状況に対応できません。これに対し、マイセーフティマップはWeb上のデータ層にある最新の情報を自動的に取得・表示するため、常に正確な情報を提供できます。潮位センサーや冠水センサーのデータといった動的な情報もほぼリアルタイムで把握可能です。
また、紙の地図では複数の情報を同時に表現するのが困難でした。マイセーフティマップでは、地図上の任意の場所をタップするだけで、その地点の浸水深や浸水継続時間、近くの避難場所といった複数の災害リスク情報をまとめて詳細に確認することができます。ユーザーは標高データやセンサー情報と連携した情報を「自分ごと」として認識でき、より迅速かつ適切な避難行動につなげられます。
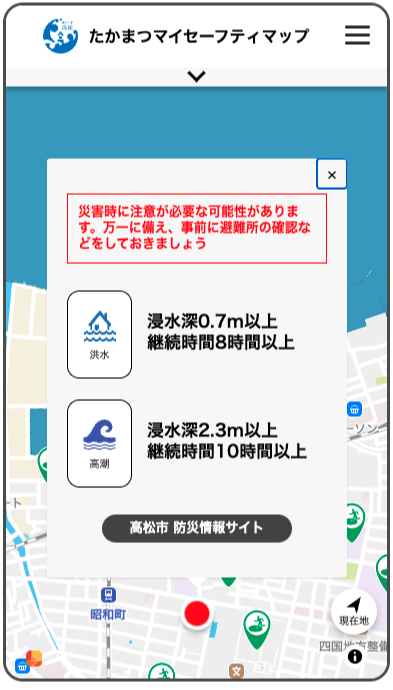
地図は「見る」から「活用する」時代へ
マイセーフティマップの事例は、機械判読性のある地図がもたらす可能性のほんの一部にすぎません。この技術は、防災だけでなく、観光、防犯、交通、都市計画など、さまざまな分野で活用の可能性を広げています。地理空間データ連携基盤を通じて機械判読性のある地図が普及することで、以下のような未来が実現されます。
- 多様なアプリケーションの創出: 開発者は、データ収集・整備の負担から解放され、防災、子育て、観光、都市計画など、様々な分野のアプリケーションを迅速かつ安価に開発できるようになります。
- データに基づいた意思決定: 行政職員は、地図上に集約されたデータを活用することで、災害対応や都市計画における意思決定を客観的なデータに基づいて行うことが可能になります。
- オープンイノベーションの加速: 標準化されたデータ形式とオープンなAPIが提供されることで、民間企業や研究者も自治体のデータを活用しやすくなり、新たなビジネスやソリューションの創出が加速します。
Geoloniaは、このような地理空間データ連携基盤を通じて、自治体が保有するデータを「機械判読性のある地図」へと変え、スマートシティの実現を強力に後押ししていきます。