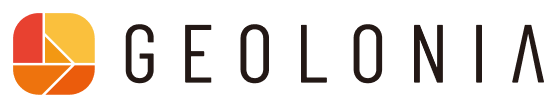低コスト・更新頻度・公共のデータの安心感が決め手


公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)のBODIKチーム
概要
ISIT(アイエスアイティー)は、福岡市の外郭団体として設立された公益財団法人です。IT分野とナノテクノロジー分野の研究開発を二つの柱としている。
オープンデータの活用を推進する現場では、日々どのような課題が生まれているのでしょうか。今回は、福岡を拠点に自治体のオープンデータ活用を支援する公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)のBODIKチームで開発を担当されている平野 真司様にお話を伺いました。自治体のリアルな悩みに寄り添い、それを解決するために生まれたツールの開発秘話と、その裏側でジオロニアのAPIがどのように活用されているのかを詳しくご紹介します。

ISIT(アイエスアイティー) 平野 真司様
―――貴団体の事業内容について教えてください。
私が所属するISIT(アイエスアイティー)は、福岡市の外郭団体として設立された公益財団法人です。IT分野とナノテクノロジー分野の研究開発を二つの柱としており、私はIT系の「オープンイノベーション·ラボ」に所属しています。
その中でも私が担当しているのが「BODIK(ボディック)」というチームです。BODIKは「ビッグデータ&オープンデータイニシアチブイン九州」の略で、設立当初はビッグデータとオープンデータの両方を扱っていましたが、現在は主にオープンデータの活用推進に特化して活動しています。
BODIKの具体的な活動としては、自治体が簡単にオープンデータを公開できるプラットフォーム「ODCS(オープンデータカタログサイト)」の提供や、日本全国のオープンデータを集約する「ODM(オープンデータモニター)」の運営を行っています。また、自治体のデータ公開業務を支援するための様々な「ユーティリティツール」を開発・提供しており、今回の主題である「BODIKジオコーダー」もその一つです。
―――「BODIKジオコーダー」を開発された経緯を教えていただけますか?
開発の直接的なきっかけは、自治体から公開されるデータに「緯度経度」が含まれていないケースが非常に多かったことです。オープンデータを集めてAPI経由で提供しようとしても、緯度経度がなければ地図上での可視化ができず、活用の幅が大きく制限されてしまいます。
自治体の担当者の方々は、住所情報は持っていても、緯度経度への変換には手段や予算の面でハードルがあるように見えました。そこで、住所から緯度経度を自動で付与できるツールが必要だと考えたのです。
いくつかのジオコーディングAPIを比較検討する中で、Yahoo!やGoogleのAPIは二次利用のライセンスに制約があり、私たちの目的には合いませんでした。その点、ジオロニアさんのAPIはすぐ利用でき、ライセンス規約が明確で使いやすかったため、採用を決定しました。
―――「BODIKジオコーダー」にはどのような工夫がされていますか?
「BODIKジオコーダー」の最大の特徴は、自動変換と手動での微調整機能を両立させている点です。APIで住所から緯度経度を自動変換しても、必ずしもピンポイントで正確な位置が示されるわけではなく、ある程度のズレが生じてしまいます。
これは、たとえ地番や建物レベルでマッチングできる高精度なジオコーダーを使ったとしても、最終的には同様の課題に直面します。例えば避難所に指定されている学校の場合、単にその住所の位置を示すだけでなく、「校舎の入り口」なのか「校庭の真ん中」なのか、目的に合わせてピンを立てたいという具体的なニーズがあるからです。そこで、自動変換後にユーザーが地図上でマーカーをドラッグし、直感的に位置を微調整できる機能を加えました。
また、背景地図も国土地理院の地図や航空写真など、複数の種類から選択できるようにしています。これにより、ユーザーは目的に応じて最も分かりやすい地図を選び、作業を進めることができます。
これらの工夫は、実際にツールを使われる自治体の担当者の方々の視点に立って実装したものです。ある時、シビックテックの活動をされている方にこのツールを紹介したところ、「もっと早く知りたかった。これまで手作業で一つ一つ調べていたんです」と大変喜んでいただけたのが印象的でした。
―――「BODIKエディタ」への進化についてもお聞かせください。
多くの自治体で、データ作成に表計算ソフトを用いられています。表計算ソフトでCSV形式のファイルを扱う際には、
- 表示形式をはじめとする書式設定や数値形式、文字コードといった点に注意を払う必要があります。
- 表計算ソフトで書式を設定して期待通りの見た目に調整しても、CSVに保存すると書式設定が保存されません。
- 保存したCSVを再度表計算ソフトで開くと、表計算ソフトによる書式の自動変換機能が働いて、見た目が変わることがあります。
この点を十分に理解しておかないと効率的には作業を進めることができません。
また、ジオコーダーのような単機能のツールを複数使い分けるのは、データの読み込みや出力の繰り返しが手間で、非効率でした。
これらの課題を根本的に解決するために開発したのが、統合型ユーティリティ「BODIKエディタ」です。このツール一つで、ジオコーディング、データ加工、住所の正規化といった、オープンデータ公開に必要な一連の作業を完結させることができます。表計算ソフトのような書式の自動変換は行わないので、データ破損のリスクがなくなり、自治体の担当者の方々の業務負担を大幅に軽減できるようになりました。BODIKのチームメンバーからも「これで自治体職員さんへのアドバイスがしやすくなった」と好評です。
―――ジオロニアのサービスに今後期待することはありますか?
ジオロニアさんのAPIには非常に助けられています。特に、熊本県内のとある町の住所が変換できなかった際に問い合わせたところ、わずか1週間で迅速に対応していただけたことには大変感謝しています。
今後の要望としては、APIの提供形態に関するものがあります。現在、住所正規化などの機能はJavaScriptライブラリとして提供されていますが、私たちの開発環境(Python)からは、Web APIとして提供していただけるとさらに使いやすくなると感じています。もちろん、オープンソースで公開されているおかげで、コミュニティの方がPythonから利用できるラッパーを開発してくださるなど、その恩恵も受けています。
―――最後に、オープンデータ活用の今後の展望についてお聞かせください。
データの「公開」はかなり進んできましたが、次のステップは「利活用」です。自治体からは「公開しても誰が使うのか」「何に役立つのか」という声が常に聞かれます。その問いに応えるためにも、公開されたデータがどのように役立つのか、具体的なアプリや可視化の事例を提示していくことが重要だと考えています。
私たちは、BODIKの活動を通じて、自治体の業務を楽にし、オープンデータが当たり前に活用される社会を目指していきたいと考えています。そのために、これからも現場の課題に耳を傾け、本当に役立つツールを提供し続けていきたいです。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
Geolonia オープンデータ活用について
住所正規化ライブラリ normalize-japanese-addresses
https://github.com/geolonia/normalize-japanese-addresses
クイック住所変換
https://quicknja.com/
住所正規化ソリューション
https://www.geolonia.com/address-normalization/